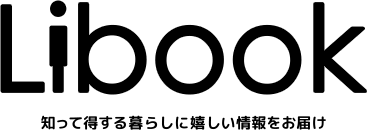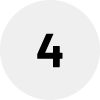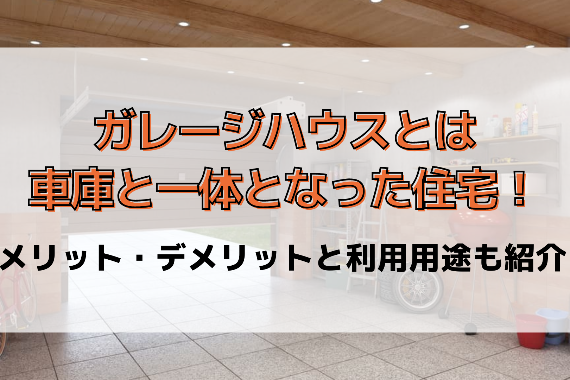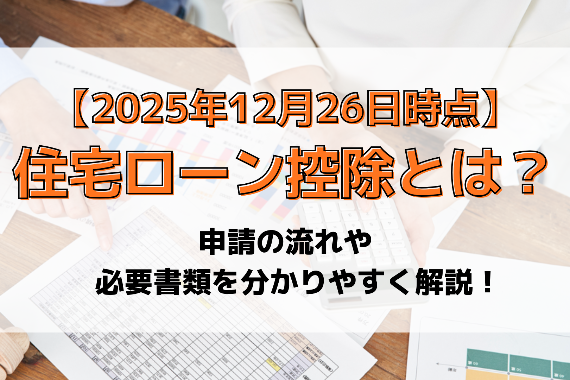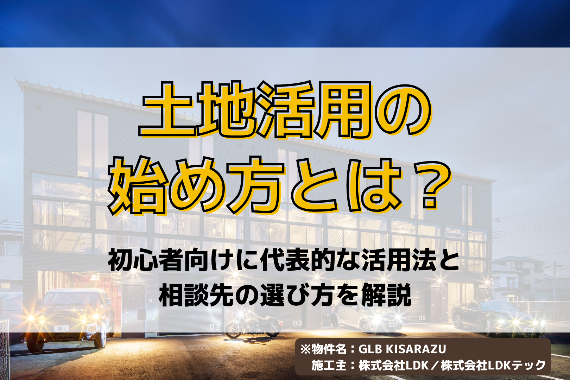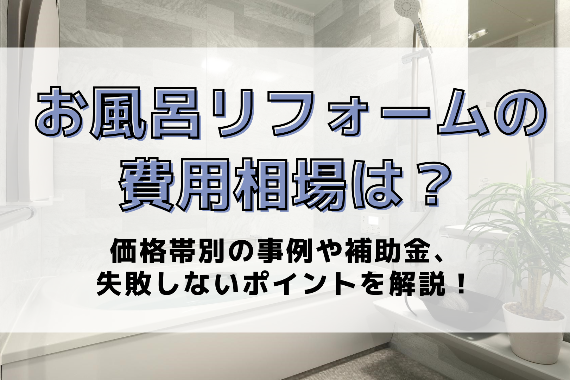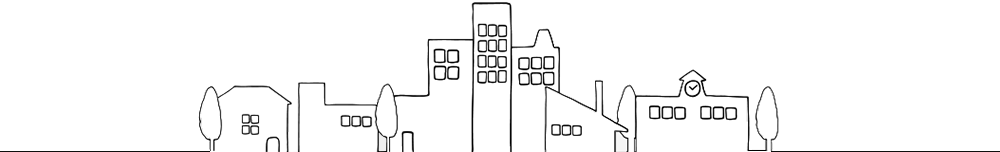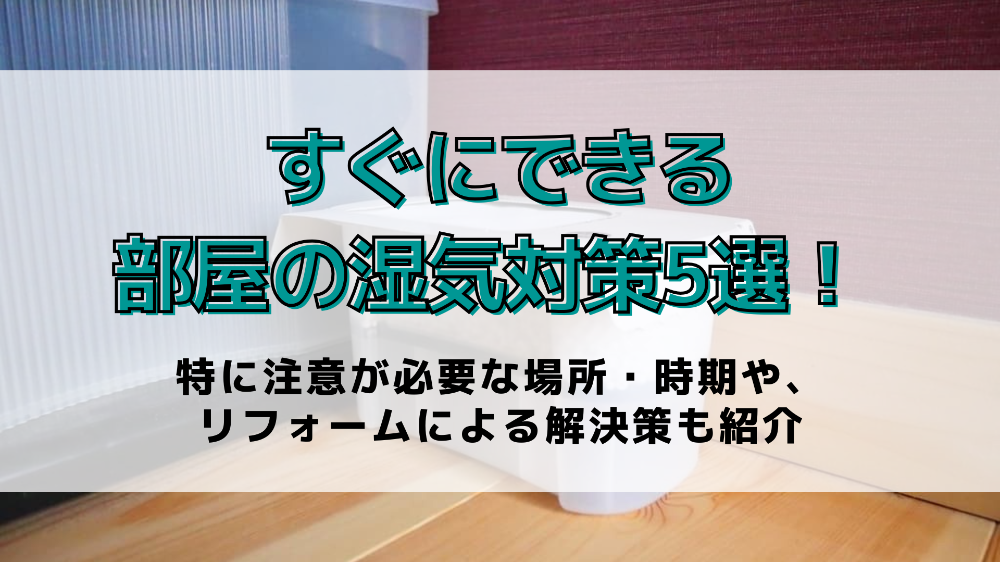
すぐにできる部屋の湿気対策5選! 特に注意が必要な場所・時期や、リフォームによる解決策も紹介

日本は高湿度な気候であるため、部屋の湿気対策は欠かせません。湿気対策を怠ると、家族の健康や家の寿命に影響を与えることもあります。
そのため「湿気対策はどのような方法が効果的なのか」、知りたい方は多いのではないでしょうか。この記事では、湿気対策が必要な場所の特徴や、今すぐできる対策、さらにリフォームを活用した湿気対策についても紹介します。部屋の湿気に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
部屋の湿気対策が必要な時期

湿度は、梅雨から夏にかけて最も高くなります。気象庁のデータによれば、2024年大阪府の月別の平均湿度は6月と7月が71%、8月は67%、9月は68%でした。一般的に湿気対策は梅雨時期に注目されがちですが、8~9月も引き続き湿度は高い状態が続くことを覚えておきたいポイントです。
また冬場は、結露による湿気の対策が必要です。冬場に暖房を使用すると、室内外の温度差が生じ、窓や壁に結露が発生しやすくなります。結露は暖かい室内の空気が冷たい窓ガラスや壁に触れると水滴となって現れる現象です。これが湿気の原因となりカビやダニの繁殖につながります。
湿度が高い時期は梅雨から秋にかけてですが、湿気対策は冬季にも必要です。
参考:気象庁
湿気対策が特に必要な部屋の3つの特徴

家の中でも、特に湿気が溜まりやすい部屋があります。こちらでは、特に注意して湿気対策を行う必要がある部屋の特徴を紹介します。
通気性が悪い
窓が少ない部屋は通気性が悪く、湿気がこもりやすくなります。また部屋のクローゼットや押し入れなどの狭い空間は、特に空気の流れが制限されるため、湿気の溜まりやすい場所と言えます。さらに日当たりが悪い部屋は、太陽光による自然乾燥効果が得られないため、湿気が溜まりやすくカビが繁殖しやすい環境です。例えば、北向きの部屋や建物の陰になる部分、地下室などは湿気対策が欠かせません。
水回りに近い
浴室やキッチンなど水回りに近い部屋は、湿度が高くなりがちです。浴室の蒸気やキッチンでの調理による水蒸気が、ドアの開け閉めにより隣接する部屋へと流れ込むためです。特に浴室の蒸気は大量の水分を含んでおり、浴室の扉を開けた瞬間に周囲の部屋へと広がります。水回りに近い部屋では、水回り使用後の換気を徹底するなどの対策が求められるでしょう。
断熱性が低い
断熱性が低い家では壁や窓が冷えやすく、室内の暖かい空気と接触することで結露が生じやすくなります。結露が発生すると部屋の湿度が高くなり、カビ発生の原因になります。例えば古い住宅は、近年建てられた家に比べて断熱材が少ないケースが多いため、冬場の湿気に注意が必要です。
部屋の湿気対策を怠ると起こる2つのリスク

部屋の湿度が高い状態を放置しておくと、健康面や住宅に悪影響を与えます。こちらでは、湿気対策を怠るリスクを解説していきます。
カビやダニが繁殖する
室内の湿度が目安として60%を超えると、カビが繁殖しダニの活動が活発になります。カビやダニは健康に悪影響を及ぼし、喘息などのアレルギー症状を引き起こす原因になります。特に影響を受けやすいアレルギー体質の方や、小さなお子さんがいる家庭では、湿気対策を十分に行うことが求められるでしょう。さらに湿度が80%を超えると、ダニの繁殖が爆発的に増加します。ダニは布団やカーペットなどの繊維製品に生息し、駆除に手間がかかるため日常的な湿気対策が欠かせません。
建材や家具が傷む
湿気が多い家では、木材が水分を吸収し腐食が進みます。さらに湿気が木材に浸透することで、シロアリの発生を招くこともあります。シロアリは湿った木材を好むため、湿気の多い環境は理想的な住処となってしまうのです。また家具や床材も、湿気によって変形や反りが生じることがあります。特に木製家具や無垢材の床は湿気の影響を受けやすいため、適切な湿度管理が家の寿命を延ばすことにも繋がります。
すぐにできる部屋の湿気対策を5つ紹介

湿気対策には、すぐに取り組めるものが数多くあります。こちらでは、具体的な湿気対策を5つ紹介します。
定期的な換気で空気を入れ替える
最も基本的な対策は、定期的に窓を開けて換気を行うことです。特に湿度が高い季節には、換気を意識的に行うと良いでしょう。朝や夕方など、外の湿度が低い時間帯に換気をすると、室内の湿気が排出されやすくなります。また、対角線上の窓を開けて空気の通り道を作ることも、効率的に湿気を排出するコツです。冬場は気温が低いため換気に抵抗感がある方も多いでしょうが、短時間でも窓を全開にして一気に換気することをおすすめします。
除湿機で湿気を取り除く
室内の湿度を効率的に下げる方法として、除湿機の使用が効果的です。除湿機で効率的に湿気を集めるには、部屋の中央に除湿機を設置することが理想です。壁や家具からは、15〜30cm以上離して設置すると効果が高まります。除湿器を選ぶ際は、部屋の広さに合ったものを選ぶことが大切です。小さすぎる除湿機では十分な効果が得られず、大きすぎると電気代がかさみます。
また、除湿の方式によっても特性が異なります。冷却コイルで水分を凝縮させ排出するコンプレッサー式は除湿力が高く、電気代が比較的安いことが特徴です。ただしコンプレッサー式は運転音が大きいため、静音性を重視する方はデシカント式を選ぶと良いでしょう。ヒーターで加熱し水分を取り出すデシカント式は、比較的電気代が高くなることに注意が必要です。
サーキュレーターで空気を循環させる
換気のしにくい風通しの悪い部屋では、サーキュレーターを使って空気を循環させることが効果的です。空気の淀みをなくし、湿気が一か所に溜まるのを防げます。特に部屋の隅やクローゼット内は空気が滞りやすいため、サーキュレーターを使って空気を送り込むと湿度を下げられます。狭い空間では湿気取りグッズを活用する
クローゼットや押し入れなど狭い空間では、塩化カルシウムやシリカゲル、生石灰を活用した除湿剤はなどの湿気取りグッズの活用もおすすめです。電気を使わずに湿気を吸収してくれるため、コンセントのない場所でも使用できます。湿気取りグッズは、床に近い場所に置くと効果的です。湿気は下に溜まりやすい性質があるため、低い位置に設置することで効率よく吸収してくれます。ただし湿気取りグッズは、水分を吸収すると飽和状態になり、効果が低下します。定期的に交換して除湿効果を維持しましょう。
窓には結露防止アイテムを活用する
窓には結露防止用のフィルムやテープを活用することで、結露の発生を防げます。断熱シートは窓ガラスに貼るだけで簡単に設置できます。外の冷気の侵入を防ぐため窓枠に断熱テープを貼ることも効果的です。また「厚手のカーテン」などの断熱遮熱カーテンを利用することで、窓ガラス付近の温度低下を防ぎ、結露の発生を抑えられます。カーテンの内側に断熱シートを取り付ければ、さらに効果を高められます。
リフォームによる、部屋の4つの湿気対策

湿気対策では、家のリフォームによって大きな効果を上げられます。こちらでは、リフォームによる湿気対策を4つ紹介します。
換気システムを導入する
24時間換気システムを導入すれば、常に新鮮な空気を取り入れながら湿った空気を排出するため、大きな除湿効果が期待できます。キッチンや浴室などの湿気がこもりやすい場所では、特に効果的です。熱交換型の換気システムでは、排出する空気の熱を回収し、取り入れる空気を温めるため、冬場のエネルギー効率を高める効果もあります。また音が静かで省エネ性の高いDCモーターの換気扇を選ぶと、ランニングコストを抑えられます。
断熱材を追加または交換する
壁や天井に使用されている断熱材を、高性能の製品に交換することで、結露の抑制効果を高めることができます。高性能断熱材が外部の冷たい空気の影響を減少させ、室内の温度が安定するため結露を抑えることが可能です。また壁や天井の内部に防湿層を設けると、湿気が内部に侵入することを防ぎ、内部結露を防げます。内部結露は目に見えにくいため気づきにくく、建材の腐敗や変形を引き起こすなど長期的に建物に悪影響を及ぼす可能性があります。リフォームの際には、断熱材と共に適切な防湿層の設置も検討すると良いでしょう。
健康建材を利用する
調湿材機能を持ち合わせたリフォーム建材の利用もおススメです。エコカラットや調湿ボード、調湿材クロスなど様々な商品があります。
窓を複層ガラスや二重サッシにする
①ガラスを複層ガラス(ペアガラス)に交換することで、断熱性能が向上し結露の発生を抑制する効果があります。複層ガラスは表面温度を維持できるため、室内外の温度差が小さくなるためです。ただ、窓枠がアルミ等の金属の場合は、窓材に結露することがありますので、注意が必要です。②既存の窓の内側に新しい窓を設置する二重サッシ化も、断熱効果を高める方法の一つです。完全に窓を交換するよりもコストを抑えながら断熱効果を得られるため、予算に制約がある場合の選択肢となります。また、窓枠と壁の隙間を適切に断熱・気密処理することも、室内外の温度差を小さくするために重要です。窓を2回開けることになりますが、防音にも効果があります。
また、既存の窓枠は残して複合樹脂アルミをカバーして、窓自体はペアガラスに変更する方法もあります(カバー工法)。上記①②の良い点を採用した工法ですが、価格は高めとなります。各種補助金が利用できる場合もありますので、ご検討の際は、調べてみることをおススメします。
部屋の湿気対策をできるところから試してみましょう

湿気対策は、住環境の快適さと家族の健康に直結するため重要です。すぐにできる対策から始めて効果を確認しながら、必要に応じてリフォームなどの対策を検討することが大切です。
まずは定期的な換気の習慣づけから始め、湿気の多い場所には除湿機や湿気取りグッズを活用しましょう。そして日頃から、室内の湿度をチェックする習慣をつけることも大切です。湿度計を設置して、60%以下を目安に管理しましょう。
また季節によって、湿気の原因や対策は異なります。夏場は外からの湿気侵入を防ぎ、冬場は結露対策を重視するなど、季節に応じた対策を行いましょう。
湿気対策は一度行えば終わりではなく、継続的に取り組むことが重要です。少しの手間と工夫で室内環境は大きく改善します。健康で快適な住環境のために、今日からできる湿気対策を始めてみましょう。