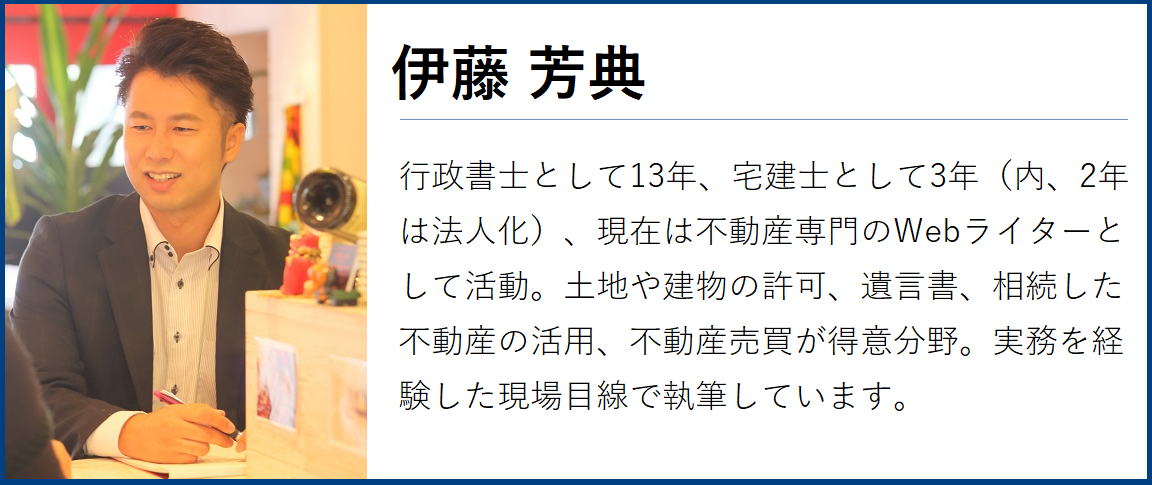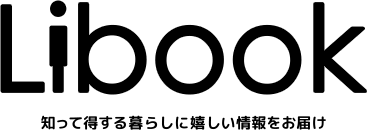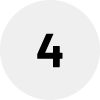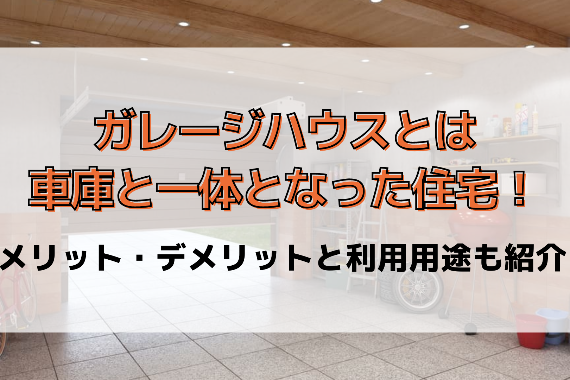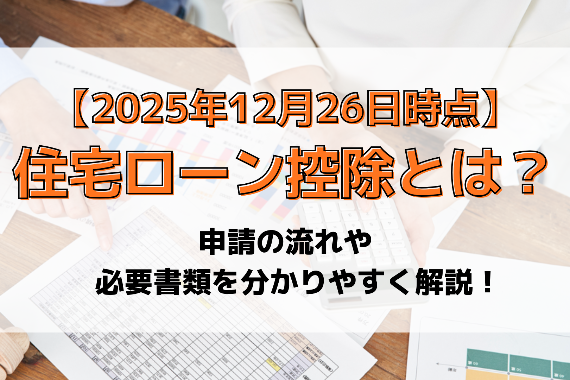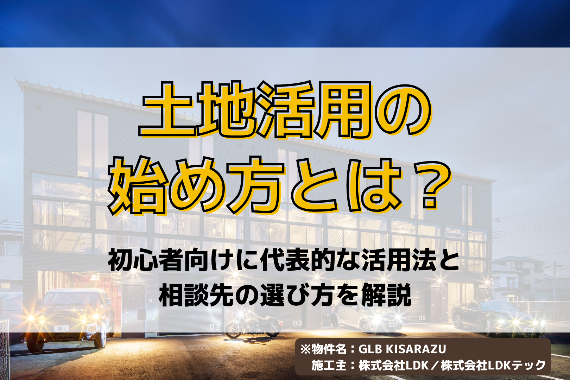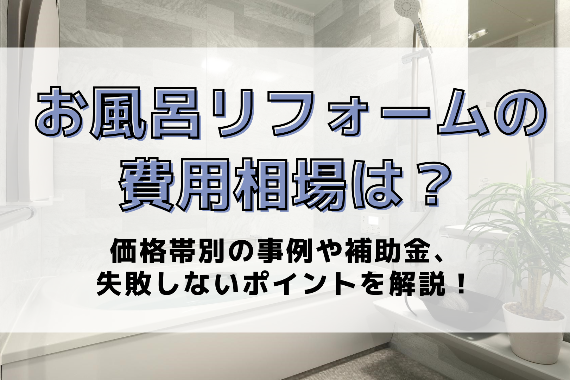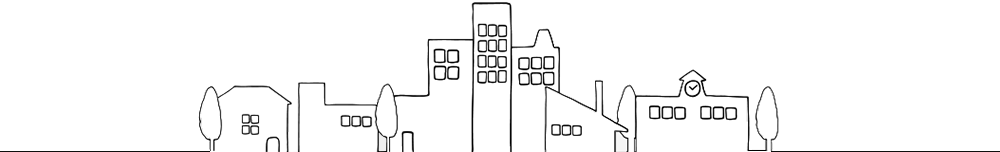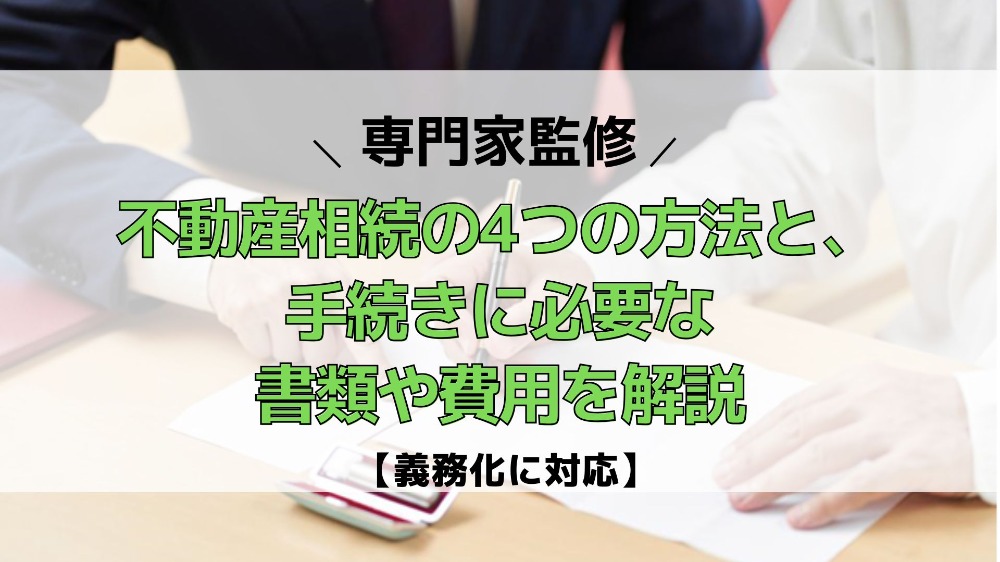

2024年4月から相続で不動産を取得した場合、名義変更の登記を3年以内に行わなければいけません。不動産相続の手続きは登記だけではなく他の手続きも必要なため、相続人には時間と労力が必要です。そのようなとき、適切に準備する知識があれば、相続手続きをスムーズに進められます。
この記事では、法改正があった相続登記の義務化の概要から手続きの流れ、必要書類や費用までをわかりやすく解説します。相続の手続きは誰もが経験する可能性があるため、万が一に備えて適切な情報と対策を身につけておきましょう。
不動産相続の登記は2024年4月から義務化

相続登記が義務化される制度は、2024年4月1日から開始されました。不動産を相続で取得したことを知った日や遺産分割が成立した日から3年以内に登記が必要です。遺言書に不備があり有効性を争っているなど、正当な理由がないのに登記手続きを怠った場合は10万円以下の過料の対象です。
この制度は過去の相続も対象に含まれます。制度開始前に所有している相続登記が済んでいない不動産は、猶予期間が3年です。2027年3月末までなので、できるだけ早く登記する必要があります。
不動産を相続する4つの方法
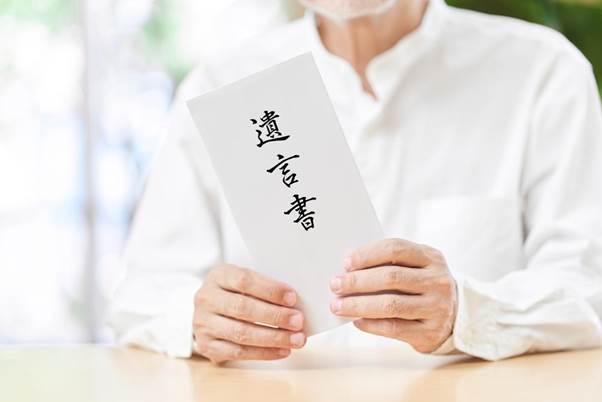
複数の相続人で遺産を相続する方法は、主に4つあります。ここでは、不動産を相続することを想定して解説します。
現物分割
現物分割は財産を現物のまま相続する方法です。たとえば、親が所有していた土地や建物を特定の相続人が単独で取得するケースが該当します。財産の形を維持しながら単独名義で相続するので、手続きが比較的簡単で相続人の負担が最小限です。しかし、財産の価値が平等にならないこともあり、相続人の間で協議がまとまらない可能性があります。
現物分割はシンプルな分割方法で、相続人全員が納得できる配分ができる場合や、分筆した土地を均等に相続できる場合に向いています。
代償分割
代償分割は、単独の相続人が不動産を相続し、他の相続人には相続分に応じた金銭や他の財産を分配する方法です。法定相続分で代償金を支払うため、他の相続人からの同意を得やすく公平に相続できます。不動産を売却せずに相続できるので、被相続人がいた自宅に相続人が住み続けたい場合に有効です。ただし代償金の支払いが必要ですので、自己資金が不足している場合は金融機関の相続ローンなどを利用しなければならない点に注意が必要です。不動産の評価をめぐって争いとなる可能性もあるので、不動産鑑定士や不動産会社に相談することをおすすめします。
換価分割
換価分割は、相続した不動産を現金化し分配する方法です。実質的には現金を分割するのと同じ状況になり、法定相続分通りに財産を分けられます。不公平感が少なく、相続税の支払いに現金が必要な場合にも有効な方法です。しかし、不動産の売却価格が想定している価格よりも安くなったり、手続きに時間がかかったりするリスクがあります。思い出のある不動産を売却することに抵抗がある場合は、他の分割方法を検討しましょう。
共有分割
共有分割は、不動産を複数の相続人が共有名義で所有する方法です。遺産分割の話し合いがまとまらない場合、ひとまず共有名義にすることで相続手続きを進められます。手続きは現物分割と同じなので、比較的簡単です。しかし、共有名義の不動産を売却する場合は共有者の同意が必要です。共有分割は分割協議がまとまらない場合に有効な方法ですが、相続人が増えると意思の統一が難しくなり不動産が放置されるリスクがあります。さらに修繕費などの費用が発生した際は、支払いの負担割合や方法について意見が合わず、トラブルになる可能性があります。
不動産を相続するための6つの手順

いざ相続することになったら、どのように進めればよいのか、悩まれる方は多いのではないでしょうか。ここでは不動産相続の流れを6つの手順で列記し、順番に解説します。
遺言書の確認
遺言書は被相続人の財産分配の意向であり、基本的には記載内容を尊重して相続手続きが進められます。したがって、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書は自宅の重要書類を保管している場所や、銀行の貸金庫へ保管していることが多いです。平成元年以降に作成された公正証書であれば、公証役場の遺言検索システムを利用して無料で検索できます。自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、法務局で閲覧できます。
公正証書遺言や法務局での保管制度を利用していない場合、遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行いましょう。検認する遺言書は、家庭裁判所に持っていき、裁判官が開封するまで見ることができません。
相続人の確定
遺産分割するために、誰が法定相続人であるかを特定します。もし、相続人が特定されないまま遺産分割協議を進めた場合、新たな相続人が発覚すると協議をやり直さなくてはいけません。法定相続人は以下の親族が該当します。| 法定相続人 | 相続の順位 |
| 配偶者 | 必ず相続人になる |
| 子(子が死亡の場合は孫) | 第1順位 |
| 親(親が死亡の場合は祖父母) | 第2順位 |
| 兄弟姉妹(死亡の場合は甥姪) | 第3順位 |
順位が上の相続人がいれば、それ以下の順位の親族に相続は発生しません。遺産分割する際には、相続人全員の同意が必要です。法定相続人は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取得して確認します。
相続財産の確定
次に、被相続人の財産をマイナスの資産も含めて全て調べます。固定資産税の納税通知書では非課税の土地が省略されることがあるので、市町村役場で固定資産評価証明書や名寄帳を取得しましょう。分割協議をするために不動産の評価額を調べる必要があり、以下の4つの計算方法があります。
- 取引価格
- 公示地価
- 路線価
- 固定資産税評価額
自身で算出することも可能ですが、相続時の正確な評価は税理士や不動産鑑定士に相談することをおすすめします。
遺産の分割協議
遺産分割協議は、相続人全員で相続財産の内容を確認し分け方を協議することです。遺言書がある場合は基本的にその内容に従って相続が進められますが、ない場合は相続人全員で協議を行い財産の分け方を決めなければいけません。遺産分割協議書は、相続手続きをスムーズにし後の争いを防ぐ目的があります。作成する際の注意点は、以下の3つです。
- 原則やり直しはできない
- 相続人全員で合意し記名押印する
- 未成年は特別代理人を選任する
不動産は簡単に分割できず、共有すると後のトラブルの原因となるので、分割方法は十分に協議することが重要です。
遺産の名義変更
2024年4月1日から施行された法改正により、不動産の相続登記は法律で義務付けられました。登記をしないと罰則の対象となるので、早めに手続きを進めましょう。相続開始の時から被相続人の不動産の権利義務を引き継ぎますが、登記をしないと他者に自分の不動産であると主張できません。遺言や遺産分割協議の内容に従い、法務局に相続登記を行います。不動産登記の専門家である司法書士に依頼すると、手続きがスムーズです。
相続税の申告・納税
相続税は、亡くなった人の財産を受け継いだ人が相続した財産の評価額に応じて負担する税金です。課税対象の不動産の相続があった場合、死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告します。期限を過ぎると税金の軽減措置が適用されなかったり、無申告加算税や延滞税が発生したりするため早めの対応が重要です。不動産の相続税評価額は、市町村役場から郵送される固定資産税通知書に記載されている「評価額」で確認できます。相続税の個別具体的な相談や税務書類の作成は、税理士に相談しましょう。税務署へ相続税の申告が完了したら、基本的には現金一括で納税します。
相続財産が3,600万円以下なら相続税はかからない

すべての相続人が、必ず相続税を支払うわけではありません。相続財産の合計額が一定額以下なら相続税の申告や納税は不要であり、基礎控除額という非課税枠を超えない限り相続税は発生しません。
相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。法定相続人の人数による基礎控除額は、以下の表のとおりです。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
たとえば、法定相続人が1人で相続財産が3,500万円の場合、基礎控除額の3,600万円以下なので相続税は発生しません。
不動産相続の際に必要な書類

不動産手続きを専門家に依頼しても、自身で準備しなくてはいけない書類があります。ここでは、相続手続きで必要となる4つの書類をどのように準備すればよいかを解説します。
遺言書
遺言書は、被相続人が自身の財産をどのように分けるかの意思を示した書類です。遺言書の作成方法は、以下の3つです。- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言は、自宅の金庫や貸金庫に保管しているケースが多いです。内容を確認するには、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。秘密証書遺言のように封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人が立会って開封しなければいけません。法務局での保管制度を利用している場合、閲覧請求や遺言書情報証明書の発行が可能です。
公正証書であれば、原本が保管されて紛失や改ざんのリスクがないので、裁判所の検認が不要です。遺言書の内容にしたがって、すみやかに名義を変えられます。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、合意した内容を文書にまとめたものです。相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を各1通添付します。印鑑証明書については、作成後3ヶ月以内といった制約はありません。分割協議書の作成期限はありませんが、相続人と相続財産が確定したらすみやかに作成します。名義変更の手続きで使用するので、作成は司法書士や行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、相続不動産の評価額の確認や登記時の登録免許税の算出で使われます。相続人であれば市町村役場で取得できる書類なので、戸籍や住民票、印鑑証明書と同時に取得するとスムーズです。発行手数料は1枚200~400円程度です。土地と建物がある場合は、それぞれ1枚ずつで合計2枚発行されます。課税されない不動産は、固定資産税評価証明書に記載されていないケースがあります。道路になっている土地や保安林の山林が相続財産に含まれる場合は、名寄帳も合わせて取得しておきましょう。
法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)
法定相続情報一覧図は、戸籍から相続関係と合致していることを登記官が確認して認証文を付した家系図のような書類です。無料で必要通数を交付でき、5年間は何度でも再交付可能です。出生から亡くなるまでの戸籍を1通ずつ準備すればよく、従来のように複数取得する必要がありません。名義変更の登記申請や金融機関の手続きの際に戸籍に代えて添付できるので、相続手続きをスムーズに進められます。令和6年4月1日から法定相続情報番号を相続登記の申請書に記載することで、法定相続情報一覧図の添付も省略できるようになりました。
相続登記にかかる4つの費用

相続登記の手続きは司法書士に依頼するのが一般的であり、費用がどのくらいかかるのか心配する方が多くいます。ここでは、不動産の相続登記で必要な4つの費用を解説します。
登録免許税
登録免許税は、不動産の相続登記をする際に収入印紙で納付する税金です。相続登記の際に、固定資産課税台帳の価格に税率0.4%を掛けて計算します。不動産の価額が100万円以下の土地は免税措置があり、登録免許税がかかりません。また、相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合も、登録免許税の免税措置を受けられます。適用期間は令和7年3月31日までであり、申請書に根拠となる条項を記載することで適用されます。
遺産分割協議書作成費用
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った結果を文書としてまとめたもので、主に遺言書がない場合に作成されます。遺産分割協議書を作成できる専門家は、以下のとおりです。| 作成できる専門家 | 特徴 | 費用の目安 |
| 弁護士 | 相続人の代理人として協議可能 | 100万円前後(代理人業務含む) |
| 司法書士 | 不動産登記を合わせて依頼可能 | 4万~12万円 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成のみ依頼可能 | 3万~8万円 |
| 税理士 | 相続税の申告を依頼する場合のみ分割協議書を作成可能 | 遺産総額の0.5~1%(申告業務含む) |
専門家によって対応できる業務が異なり、遺産分割協議書以外で必要なサポートを基準に選ぶのがよいでしょう。たとえば不動産の相続がある場合は、相続登記と併せて司法書士に依頼することが多いです。遺産分割協議書のみを依頼する場合の費用は3万円からが相場ですが、相続財産や分割方法などにより費用は変動するため、事前に確認しましょう。
住民票・戸籍謄本
相続手続きには住民票や戸籍謄本が必要であり、市町村役場で取得する際の費用は以下のとおりです。| 書類 | 費用の目安 |
| 住民票 | 300~400円 |
| 戸籍謄本 | 450~750円 |
| 印鑑証明書 | 200~400円 |
亡くなった方の住民票は「除票」といい、相続人であれば取得できます。戸籍は複数の呼び名があり、戸籍から全員がいなくなると「除籍」、法改正により古くなった戸籍は「改製原戸籍」と呼ばれます。相続手続きでは生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要なので、除籍や原戸籍を含めて複数の戸籍謄本を取得しなくてはいけません。
基本的にはどの相続手続きでも原本が必要であり、それぞれ2~3部ずつ取得するとよいです。不動産の他にも名義変更を必要とする財産がある場合は、戸籍謄本の代わりに無料で取得できる法定相続情報一覧図を添付することで費用を抑えられます。
司法書士報酬
登記書類の作成は司法書士の独占業務であり、相続登記が義務化されたことで依頼を検討する方が増えるでしょう。日本司法書士連合会報酬額アンケート結果によると、相続登記の司法書士の報酬額は約5~8万円です。報酬額は不動産や相続人の数により変動するので、依頼前に見積もりをとって確認が必要です。必要書類の取得や分割協議書を自身で作成することで費用を抑えられる場合があるので、司法書士に相談してみましょう。
義務化された不動産登記の手続きを今のうちに理解しておきましょう

相続登記が2024年4月から義務化され、不動産取得後3年以内に登記申請しなくてはいけません。違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続には登記をはじめとするさまざまな手続きが必要であり、スムーズに進めるために事前の準備が重要です。手続きの流れやかかる費用を把握しておけば、判断に迷うことなく安心できるでしょう。相続が発生したら、後のトラブルを防ぐためにも司法書士などの専門家に相談し、早めに手続きを進めることをおすすめします。